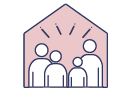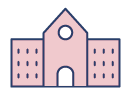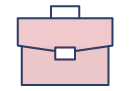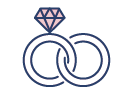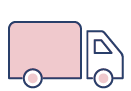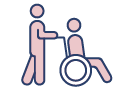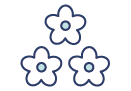地域猫活動
飼い主のいない猫による被害(フンや鳴き声等)を軽減するための新しい取り組みとして、地域猫活動という活動が全国で広がっています。
地域猫活動とは、飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施したのちに、継続して管理(餌やり・トイレの設置等)することで、一代限りの生を全うさせるとともに、生まれてくる子猫を減らすことで将来的に飼い主のいない猫をなくしていくことを目的とした活動のことです。
地域猫活動は地域住民が主体となり、飼い主のいない猫によって生じる被害を、単なる「猫」の問題ではなく「地域の環境問題」としてとらえることで、猫による諸問題を解決していきます。
なお、地域猫活動を実施するにあたっては、あらかじめ地域住民に対して丁寧な説明をし、活動についての理解をしてもらうことが大切です。また、活動開始後も、結果を地域住民で共有し、活動に対する成果を感じることで、更に理解を深めていくことが大切です。
地域ねこ活動をするための流れ(概要)
- 情報収集と地域住民への事前説明
関係各所への相談(ボランティアや行政等) - 役割の決定
主な役割:猫の保護、不妊去勢手術、餌の管理、トイレの管理 - 地域猫活動の実施について地域に周知
- 手術実施
実施後は猫の耳にV字カットするなど、手術実施猫と分かる識別をする - 猫を元の場所に戻す
- 周辺環境の保全を続ける
具体的には- 餌の管理(餌の置きっぱなしはダメ!)
- 猫用トイレの設置・管理
- 新たな猫が現れた際の、不妊去勢手術の実施
- 地域住民へ活動報告
- 定期的な関係各所との情報共有
地域猫活動の効果
飼い主のいない猫が増えるのを防ぎます。
餌やりトラブルやフン尿被害が低減します。
地域のつながりが豊かになります。また、動物の命を大切にすることへの気運が高まります。
地域猫活動を進めるうえでの注意点
地域の理解を得るために時間がかかる場合があります。
猫を元の場所に戻して寿命を全うさせるため、効果が現れるまでに時間がかかります。
地域猫活動を進めるために大切なこと
地域猫活動には、地域住民・ボランティア・行政の三者の協働が大切です。
三者の役割
- 地域住民:不妊去勢手術の実施、エサの管理、猫用トイレの設置、管理、周知
- ボランティア:地域住民の活動のサポート、助言
- 行政:地域猫についての広報、各種連絡調整、不妊去勢手術助成金等
猫の被害で困っている人や、猫が苦手な人への配慮も大切です。また、猫に餌を与える人や、猫が好きな人、そもそも猫の被害を受けてない人など、様々な立場の人が地域に住んでいることを理解しながらすすめることが大切です。
最初に地域猫活動に取り組む際にはボランティアに協力してもらうのが理想的ですが、ノウハウを教えていただいたあとは、地域住民が自立して活動を行っていく必要があります。
その他
「倉敷市飼い主のいない猫不妊去勢手術費助成金制度」(倉敷市ホームページ)を地域猫活動に利用することもできます
参考リンク・関係資料/チラシ
全国の実例紹介
地域猫活を周知するための資料
※地域の実情によっては別の資料が適している場合もあります
お気軽にご相談ください
猫の飼い方についての啓発資料
※地域猫活動を始めるにあたっては地域で飼い猫が適正に飼養されていることが大切です
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市保健所 生活衛生課 動物管理係
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:086-434-9829 ファクス番号:086-434-9833
倉敷市保健所 生活衛生課 動物管理係へのお問い合わせ