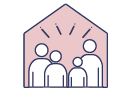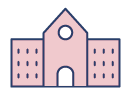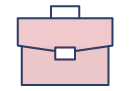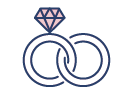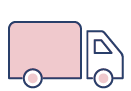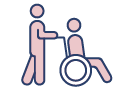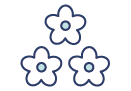不足額給付のよくある質問
- Q1.令和6年11月に他市から転入して、令和7年1月1日は倉敷市に住んでいます。当初調整給付は転入前の自治体から給付されましたが、不足額給付はどの自治体から案内が届きますか
- Q2.源泉徴収票(給与・年金)に控除外額が表示されていますが、その額が給付されるのですか
- Q3.令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族の人数))にならないのはなぜですか
- Q4.不足額給付は課税対象になりますか
- Q5.当初調整給付を申請しておらず受給していない場合、不足額給付で当初調整給付分も含めて支給してもらえますか
- Q6.不足額給付の対象者が死亡、または死亡している場合どのような取り扱いになりますか
Q1.令和6年11月に他市から転入して、令和7年1月1日は倉敷市に住んでいます。当初調整給付は転入前の自治体から給付されましたが、不足額給付はどの自治体から案内が届きますか
A1.不足額給付の実施自治体は、令和7年1月1日に居住している自治体(令和7年度住民税課税自治体)になります。そのため、他市で当初調整給付を受給されていた場合でも、令和7年度住民税課税地が倉敷市であり、不足額給付の対象と思われる場合、倉敷市から案内が送付されます。
Q2.源泉徴収票(給与・年金)に控除外額が表示されていますが、その額が給付されるのですか
A2.源泉徴収票に記載されている控除外額は、その課税資料のみで計算された所得税分となります。不足額給付は、すべての所得と控除により再計算され、かつ当初調整給付との差額による不足分のみが支給されるため、源泉徴収票に記載されている金額が支給されるものではありません。
Q3.令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族の人数))にならないのはなぜですか
A3.令和6年の源泉徴収票には所得税(4万円のうちの3万円分)の定額減税分のみ記載されています。個人住民税の定額減税分(4万円のうちの1万円分)については記載されていません。個人住民税の定額減税分については、「令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書」を確認してください。
Q4.不足額給付は課税対象になりますか
A4.課税対象ではありません。そのため申告も不要です。また差押えの対象にもなりません。
Q5.当初調整給付を申請しておらず受給していない場合、不足額給付で当初調整給付分も含めて支給してもらえますか
A5.当初調整給付を受給していない場合であっても、当初調整給付との差額分のみの支給となります。
Q6.不足額給付の対象者が死亡、または死亡している場合どのような取り扱いになりますか
- Q6-1.「支給確認書」が届いた場合
支給確認書提出前にお亡くなりになった場合、受給権がありません。
支給確認書提出後にお亡くなりになった場合、相続人が受給できます。ただし、支給確認書提出時に記入した振込口座が凍結されているなど、振込できない状態になっている時は、倉敷市不足額給付金コールセンター(電話:0120-011-792、平日9時から17時)へ連絡してください。
- Q6-2.「支給のお知らせ」が届いた場合
「支給のお知らせ」の確認期限である8月7日以前にお亡くなりになった場合、受給権がありません。
8月8日以降にお亡くなりになった場合、相続人が受給できます。ただし、 支給のお知らせに記載されている振込口座が凍結されているなど、振込できない状態になっている時は、倉敷市不足額給付金コールセンター(電話:0120-011-792、平日9時から17時)へ連絡してください。
※書類の印刷時期の関係で、お亡くなりになった方宛に書類が届く場合があります。申し訳ありませんが、ご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 臨時特別給付金室
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地