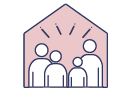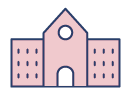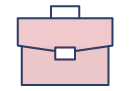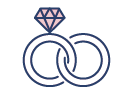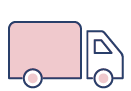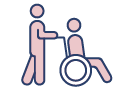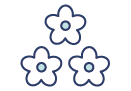2024年2月の所信表明

議員の皆様、本日は、御多忙の中お集まりいただき、厚くお礼を申し上げます。それでは、令和6年度諸議案の提案理由説明に先立ちまして、今議会は、私にとりまして今任期、最後の市議会となりますので、御挨拶も申し上げさせていただきたいと存じます。
はじめに、私の4期目は、倉敷市始まって以来の未曽有の大災害である平成30年7月豪雨災害からの真備地区の復興に向けて取り組んでまいりましたが、それと同時に、令和2年1月に国内初の感染が確認され、その後感染が拡大した新型コロナウイルス感染症との闘いが続き、さらに令和4年10月から11月には市内の養鶏場で、高病原性鳥インフルエンザが3例連続して発生し、また、世界情勢の変化により今なお続く原油価格・物価高騰等が市民の皆様の暮らしや地域経済に大きな影響を与えるなど、大変難しい舵取りを迫られる4年間でありました。
新型コロナウイルス感染症については、令和2年1月31日に倉敷市新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、令和2年5月8日に第1例目の感染者が確認されてから、令和5年5月8日に感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同じ5類感染症となるまでの3年余りの間に、累計で12万人を超える市民の方が感染者として届出されました。
この間、倉敷市連合医師会、倉敷中央病院、川崎医科大学附属病院をはじめとする医療機関や社会を支えるエッセンシャルワーカーの皆様の大いなる御尽力と、市民の皆様と事業者の皆様の御協力により、医療体制の確保、感染対策、ワクチン接種をはじめとする数々の対策を行うことができ、苦難を乗り越えてまいりました。また、感染拡大により大きく影響を受けた市民生活や地域経済を支える多くの事業にも取り組んでまいりました。これもひとえに皆様の御協力のおかげと心より感謝申し上げます。
さて、私は、今期の任期の中で、公約のテーマを「災害からの復興とみらいに向かうまちづくり」として、公約に5つの政策である「真備地区の復興推進と、災害に強いまちづくり」「子育てするなら倉敷でと言われるまちづくり」「温もりあふれる健康長寿のまちづくり」「個性と魅力ある文化と産業を育む活力あるまちづくり」「みらいに向かって持続可能なまちづくり」を掲げて取組を進めてまいりました。この4年間の主な取組につきまして、御報告させていただきたいと存じます。
第1に「真備地区の復興推進と、災害に強いまちづくり」の実現につきましては、真備地区の復興を着実に進め、倉敷市全体で防災教育の推進や地区防災計画策定などの防災・減災への備えを進めることで、災害に強いまちづくりに取り組んでまいりました。
災害直後から現在まで、今、何が求められていて、何から行っていくべきなのか、復興の段階に応じて被災された皆様が望まれているのは何か、これらのことを皆で共有しながら、復興への道を進めていくことが私の役割と考え、被災された皆様の真備での生活を取り戻したいという思いを胸に、治水対策や生活再建、経済活動の復興などを進めてまいりました。被災された皆様のたゆまぬ努力をはじめとして、多くの皆様からの復興に向けた御支援に、改めまして心から感謝を申し上げます。
真備地区復興計画の推進については、小田川合流点付替え事業をはじめとする真備緊急治水対策事業や、被災された皆様の住まいや生活、事業の再建、まちの賑わいを取り戻すことなど、着実に進んでいるところでございます。今後も、被災された皆様が、一日も早く安心して落ち着いた生活を取り戻していただけるように、引き続き全力で取り組んでまいります。
平成30年7月豪雨災害をふまえた災害に強いまちづくりにつきましては、令和2年8月に、市では「倉敷市総合防災情報システム」、市民の皆様に向けて防災情報を集約した「倉敷防災ポータル」の運用を開始し、また、必要な方に緊急告知FMラジオを活用していただくため購入補助制度も開始しました。
防災備蓄の強化については、支援と受援を円滑に行うことができるようにするために、市内外からアクセスしやすい拠点を設けることとし、令和3年3月に阿津防災備蓄倉庫を整備し、さらに有城防災備蓄倉庫の整備を進めています。また、山陽ハイツ跡地には都市防災公園の整備を進めています。
災害時においては、特に初期の段階で飲料水やトイレの確保が重要となってくることから、令和4年度と令和5年度で、倉敷・児島・玉島・水島・真備に、それぞれ10万リットル(約1万1千人分の3日間必要量)が確保できる耐震性貯水槽を整備しており、また、平成23年度から取り組んできている災害時に備えたマンホールトイレについては、令和5年度までに、下水道区域内にある小学校・中学校・支援学校の合計70校に487基を設置しました。
浸水対策としては、8か所の排水機場で排水能力向上や老朽改修を行い、さらに2か所で排水機場の新設に取り組んでいます。河川・遊水池浚渫を8河川14か所で実施、ため池47池で浚渫・改修・廃止等に取り組んでおり、またこれまでに、ため池184池についてハザードマップを作成しています。倉敷市独自の浸水対策としては、農業者の皆様の御理解のもとで、豪雨に備えて農業用水路の事前排水を行うことで約300万トンの貯水容量を確保する取組や、田んぼダムの取組も行っています。また、令和3年度には、倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例を制定して、行政・市民・事業者が協力して浸水対策に取り組むこととしており、これまでの家庭用雨水タンク設置補助などに加えて、開発行為等を行う場合に雨水流出抑制施設整備の協議を行うこととし、現在までに約30件で2千トンの貯留量が見込まれています。
地区防災計画については、地域コミュニティにおける共助による防災活動推進の観点から、地域の方々が自ら考え防災活動の計画策定に取り組んでいただくものですが、令和2年からのコロナウイルス感染症の影響で、地域で集まることが難しい状況が続きましたが、現在までに37地区が策定済み及び策定中の状況となっています。
また、平成30年7月豪雨災害をふまえて、防災教育の推進を図ることとし、令和2年度から小学校全校の3年生及び5年生に、令和4年度から中学校全校の2年生を対象に、それぞれ新たに3時間以上の防災学習に取り組んでいます。小学校では、地域で起こりうる災害のリスクや、避難行動・避難場所の確認、通学路の防災安全マップの作成、洪水・土砂災害に備えたマイ・タイムラインの作成を通じて、家族とともに考え学び、防災意識や実践力を高め、中学校では、過去の災害を振り返り、今後発生が想定される災害への備えについて、「自助」に加え、「共助」の視点で考えることができるようにしています。
第2に「子育てするなら倉敷でと言われるまち」の実現につきましては、安心して妊娠・出産・子育てができ、子どもたちが、それぞれの個性と能力を伸ばし、自らの未来を切り拓いていく力を身につけられる環境づくりに努めてまいりました。
まず、結婚・妊娠・出産への支援として、妊婦・子育て相談ステーションすくすくの相談員を12名に増やして相談体制を充実するとともに、子育て親子の情報交換、託児等の場となる地域子育て支援拠点を老松小学校区に拡充するとともに、様々な支援施策の相談ができる専門窓口をくらしき健康福祉プラザに開設しました。また、令和4年11月に倉敷北児童センターを移転新築しました。助産所等で保健指導などを行う産後ケアの利用期間延長や利用者負担の更なる軽減を図りました。また、子ども医療費の公費負担を、令和5年7月から通院分についても中学校3年生までに拡大しました。
待機児童対策としては、保育所、認定こども園、事業所内保育施設、小規模保育施設で合計444人の受入れ増を行いました。令和3年度入所手続きよりAIを活用した入所事務支援システムを導入し、よりきめ細かな入所調整を行い、保育士確保のための市独自の処遇改善や事務のICT化などによる負担軽減、保育士・保育所支援センターを中心とした離職防止対策研修会の実施に加え、高校や保育士養成校への出前授業や市内5校の保育士養成校の連絡協議会の立ち上げ等により市内の高校から市内の養成校へ進学し、市内の施設へ就職する流れを創出するなど「保育士・幼稚園教諭になるなら倉敷で」となるように取り組むなど、受入れ増と保育士確保対策を両輪として進めることにより、待機児童数は18人まで減少しました。また、保護者の就労を支援するため、幼稚園の預かり保育実施園を5園、3歳児保育実施園を3園それぞれ拡大しました。放課後児童クラブについても、施設等の環境整備を進めることで、合計541人の受入れ増を行いました。
学力向上支援、英語教育の強化につきましては、英語力向上を目的として、令和2年から小学校5年・6年に英語音読教材アプリを導入し、また、非常勤講師や学習支援員を充実しています。教育環境の整備として、平成28年度から計画的に進めてきた学校園へのエアコン設置につきましては、この4年間で幼稚園遊戯室及び保育室、小学校特別教室、中学校特別教室、高等学校普通教室の830教室に設置し、今年度中にすべての教室にエアコンを配備できる予定です。また、小中学校のトイレ洋式化についても、この4年間で57パーセントまで進みました。また、水島地域には県立高校が1校のみのため、市立高等学校の適正配置計画に基づき、旧霞丘小学校校舎を改修して市立精思高等学校の分校霞丘校を本年4月に開校予定です。また、市内初となる義務教育学校の設置を、令和8年4月の開校に向けて下津井地区において進めているところです。
第3に「温もりあふれる健康長寿のまち」の実現につきましては、スポーツや社会・文化活動を通じて健康増進を図り、医療や介護の充実などにより、誰もが人との関わりのなかで生活を楽しめる健康長寿のまちづくりに取り組んでまいりました。
まず、スポーツの推進、フレイル対策・認知症予防の推進につきましては、水島緑地福田公園の体育館耐震補強・大規模改修に続いて、令和4年3月までに床修繕を行うとともに、テニスコートを4面増設し、人工芝のサッカー・ラグビー場も令和5年2月に新設しました。天然芝のサッカー・ラグビー場についても令和6年4月に供用開始できる見込みです。
令和4年7月には、倉敷児童館、有城荘、ふじ園を複合施設「くらしきすこやかプラザ」として整備、西岡荘を旧倉敷北児童センターの増改築により倉敷北高齢者福祉センターとして整備、また、市内最後となる万寿東憩の家を令和5年10月に整備しました。
また、高齢者の方々の社会参加や介護予防等につながるふれあいサロンは、活動団体数が令和元年度末の257団体から令和6年1月末には313団体に、認知症の方や家族を支援する認知症カフェも、令和元年度の17団体から令和6年1月末には25団体となっています。
医療・介護体制の強化の取組として、新型コロナウイルス感染症対応や、今後の災害への備え等に対応するため、倉敷市連合医師会や倉敷市内歯科医師会協議会等との連携を強化し、また、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画等に基づいて、地域密着型特別養護老人ホームや小規模多機能型居宅介護施設等の整備を進めてきたほか、介護現場への介護ロボットやICT導入の支援を行うなど、地域で安心して暮らせるための環境整備や介護従事者の負担軽減に努めました。
第4に「個性と魅力ある文化と産業を育む活力あるまちづくり」の実現につきましては、世界に誇る自然・伝統・文化を育むとともに、産業の競争力強化や企業誘致、移住定住推進や若者の地元就職促進などを図ることにより、活力あるまちづくりを進めてまいりました。
地域の伝統・文化の振興や、豊かな自然や歴史的町並み、3つの日本遺産による観光客誘致の推進につきましては、まずは、将棋と囲碁のまちとして、大山康晴十五世名人の生誕100周年にあたり、第80期名人戦七番勝負第5局や、第77回全日本アマチュア将棋名人戦全国大会等を、また、真備の復興につなげるべく、第46期碁聖戦や、囲碁サミット2023inくらしきを開催しました。また、3つの日本遺産を有するまちとして、第33回北前船寄港地フォーラムinOKAYAMAを開催し、日本遺産の構成文化財であり弥生時代最大級の墳丘墓として全国から注目を集める楯築遺跡については、保存活用計画を策定して遺跡内にある給水塔の撤去を進めることといたしました。
また、歴史的町並みの魅力向上に向けて取り組んでいた、美観地区の電線類地中化2.64キロメートルについて令和3年度で完了したほか、10年の歳月をかけて取り組んだ国の指定重要文化財であり美観地区で最も古い町屋といわれる井上家住宅の保存修理工事が完了し、江戸時代天保年間の倉敷町屋の姿が甦りました。また、倉敷市まちづくり基金を活用した市内各地区の町家・古民家再生も進んでおり、まちの新たな賑わい創出につながっています。
また、昨年4月には、平成28年のG7倉敷教育大臣会合に続いて倉敷市で2回目となる「G7倉敷労働雇用大臣会合」が倉敷美観地区において開催され、世界各国から多くの関係者が参加し、「人への投資」をテーマに議論が交わされ、「G7倉敷こどもサミット」や「G7倉敷労働雇用大臣会合記念シンポジウム」の内容も反映された「G7倉敷労働雇用大臣宣言」が採択され、世界に発信されるとともに、会合開催の背景となった倉敷市の歴史や文化、産業も世界に発信されたことで、今後のインバウンド需要やMICE誘致にもつながり、大きな経済効果も生まれました。
また、産業の競争力強化、企業誘致・設備投資の推進等については、令和4年5月に新たな商工業活性化ビジョンを策定し、産業人材の確保・育成、持続可能な地域経済の実現などに取り組んできました。企業誘致では、この4年間で6社の新規立地、2社の本社機能の移転、設備投資促進奨励金制度では、40社75件で約2,583億円の投資につながりました。また、国に対して、強く要望を続けてきた結果、令和2年度には玉島ハーバーアイランド7号埠頭の供用開始、令和3年度には旧瀬戸埠頭の公共埠頭化、昨年末の水島玉島航路の水深12メートル化浚渫工事完了につながり、国際バルク戦略港湾水島港の更なる競争力強化となっています。
地場産品の競争力強化については、特産品である桃・ブドウなどの高収益化に取り組む農業者に、施設整備助成を行いました。また、米の地産地消推進と食料自給率向上、小麦粉価格高騰対策として、令和4年度から米粉利用の普及啓発や、令和5年10月には米粉製粉機の導入も行いました。
また、移住定住推進や地元就職支援につきましては、新たに下津井地区に設置した移住検討者が利用する「お試し住宅」の利用も好調で、既設の玉島地区と合わせて、この4年間で418人の利用があり、うち88人が移住されました。また、若者の地元就職支援として、中学・高校に地元企業を派遣して企業の特徴や魅力を体験する講座の開催などに取り組んでいます。
第5に「みらいに向かって持続可能なまちづくり」の実現につきましては、環境にやさしく都市機能が充実した暮らしやすいまちをつくるとともに、高梁川流域自治体との連携をより一層強化することで、みらいに向かって持続可能なまちづくりに取り組んでまいりました。
まず、市民協働による地球温暖化対策の推進に関する取組として、2050年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」にチャレンジしていくことを令和3年6月に表明しました。これまでに、太陽光発電・太陽熱利用・家庭用燃料電池・リチウムイオン蓄電池の設置、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)整備、さらに、電気自動車及びV2Hに対する助成など、様々な取組を行っております。市内における住宅用太陽光発電パネルの設置件数でみると、令和5年9月末現在、22,363件と、全国の市区町村で第8位、中核市では第1位の設置件数となっています。また、本年度実施した省エネ家電買替え促進事業では、約3,000件の申請があり、東京ドーム約17個分の二酸化炭素削減効果がありました。また、令和4年4月に、水島コンビナート立地企業とともに「水島コンビナートカーボンニュートラル研究会」を設置し、先進地視察やセミナー等を行い、カーボンニュートラルに向けた機運を醸成することで、令和5年3月の「水島コンビナートのカーボンニュートラル実現に向けた取組方針」の取りまとめにつなげました。さらに、高梁川流域の自治体にも取組の輪を広げ、高梁川流域カーボンニュートラル研究会を設置し、二酸化炭素削減に向けた調査・検討を行いました。こうした取組により、令和3年度の温室効果ガスの排出量は、基準年度である平成25年度比で13.3パーセント減少するなど、2050年までのゼロカーボンシティ達成に向けて取組を進めています。
建替えが必要となった倉敷西部清掃工場と水島エコワークスと東部粗大ごみ処理場につきましては、これらの機能を統合した新たなごみ処理施設として、令和7年4月の本格稼働に向けて(仮称)倉敷西部クリーンセンターの整備を進めています。また、同じく既存施設の老朽化により建替えが必要となった中央斎場についても、近年の高齢化の進展なども踏まえて、新たな施設を整備し、令和6年4月に供用開始します。
次に、中心市街地活性化など都市機能の充実につきましては、倉敷駅周辺地区の活性化の核となる阿知3丁目東地区市街地再開発事業「あちてらす倉敷」が令和3年10月にグランドオープン、4月にJR倉敷駅から市立美術館までの区間を景観形成重点地区等に指定するなど、歴史的な町並みと都市景観の調和したまちづくりを進めてきました。JR山陽本線等倉敷駅付近連続立体交差事業につきましても、市は倉敷駅周辺第二土地区画整理事業を着実に推進するとともに、事業主体である県や関係機関と引き続き、協議・検討を行っております。また、幹線道路整備として、都市計画道路である柏島道越線、西阿知矢柄線の整備を進め、水島臨海鉄道についても、ホームに列車接近表示及び放送設備を設置することとしています。
次に、高梁川流域自治体で連携した取組としては、「高梁川流域圏成長戦略ビジョン」に基づき、産業振興や、福祉や住民サービスの充実、ゼロカーボンやDXの推進など合計71事業で取組を進めており、令和2年7月には、国からSDGs未来都市及び自治体SDGsモデル事業に選定されました。今後も連携強化を図ってまいります。
行財政改革の推進につきましては、「行財政改革プラン2020」に基づき進めており、4年間で約56億円の効果目標に対して、令和4年度までの3か年で目標を上回る約110億円の効果をあげております。また、負債の削減につきましては、全会計の借入金については、令和5年度末の数字が確定しておりませんので、臨時財政対策債と豪雨災害関連市債を除いて、令和元年度末の2,524億円から令和4年度末には2,251億円と、約273億円の削減となっております。
また、ふるさと納税制度は、地場産業の活性化にも大きく寄与することから、庁内の横断的組織「ふるさと納税推進検討会」を発足して、新規協賛事業者や新たな返礼品の開拓を図りつつ、寄附受付サイトの拡充や様々な広告戦略に取り組んできたことで、寄附金額は令和2年度の約9千万円から、令和5年度末には約7億円への増加を見込んでおります。
また、公共施設の長寿命化・複合化等を図るため、倉敷市庁舎等再編整備、児島地区公共施設再編整備及び水島地区公共施設再編整備などを進めております。
以上、公約に掲げました5つの政策への主な取組について述べさせていただきましたが、このように取組を進めることができておりますのは、ひとえに市議会の皆様並びに市民の皆様の御理解と御協力があればこそのものであり、心より厚くお礼を申し上げる次第でございます。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市長公室 秘書課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3003 ファクス番号:086-427-5400
倉敷市への提案は市民提案メールを使用してください。